本日もお越し頂きありがとうございます!
ウイスキーを愛する料理人Yaffeeです。
今回のお話は、「ウイスキープロフェッショナル」についてです。
ウイスキー文化研究所が行っているウイスキーの資格制度「ウイスキーコニサー」。
ウイスキーコニサー資格の中でも
- 「ウイスキーエキスパート」
- 「ウイスキープロフェッショナル」
- 「マスター・オブ・ウイスキー」
の3ランクがあり、その2番目の資格となるのが「ウイスキープロフェッショナル」です。
今回はウイスキープロフェッショナルとは何なのか?
ウイスキープロフェッショナルの資格を取得するメリット・勉強方法とは?
についてまとめていこうと思います。
また最後に「ウイスキープロフェッショナル」に向けて、簡単な模擬問題を作ってみました!
ウイスキープロフェッショナルの試験を受けようと思う方は参考にしてみてください。
ウイスキー文化研究所認定
ウイスキープロフェッショナルとは?

ウイスキーの資格制度「ウイスキーコニサー」。
第1段階の「ウイスキーエキスパート」は「筆記試験」のみだったのに対して、
第2段階の資格である「ウイスキープロフェッショナル」は「記述を含む筆記試験」と「官能テイスティング試験」。
この試験に合格した方は、「ウイスキー文化研究所認定ウイスキープロフェッショナル」と名乗ることができ、「ウイスキーレクチャラー(ウイスキー講師)」養成講座を受ける資格を得ることができます。
ウイスキー文化研究所とは?

ウイスキー文化研究所(旧スコッチ文化研究所)は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務める会員制の愛好家団体です。その対象はスコッチウイスキーにとどまらず、広く世界のウイスキーとその文化を学ぶため、日々研究、情報の収集、そして発信を行っています。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー、酒文化全般をより深く知るため、研究範囲と活動を拡げ、そこに関わる多くの人々と様々な取り組みを企画・立案、実施してきました。と同時に、愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及にも努めています。スコッチやその他のウイスキーに興味のある方、あるいは当研究所が主宰する ウイスキーコニサー資格認定試験 や ウイスキー検定 に興味のある方なら、どなたでも会員になれます。
(引用:ウイスキー文化研究所、「ウイスキー文化研究所とは」より)
ウイスキー文化研究所とは、日本のウイスキー評論家:土屋守さんが代表を務めるウイスキー愛好家団体です。
会員制の団体となっていて、ウイスキー文化研究所会員には、隔月で同団体が出版している「ウイスキーガロア」が届きます。
その他会員特典として、ウイスキーセミナーやイベントなどの優先チケット・特別割引、会員限定のウイスキーなどもあります。
そのウイスキー文化研究所が行っているウイスキーの資格制度が「ウイスキーコニサー」です。
ウイスキーの資格制度『ウイスキーコニサー』とは?

「コニサー」とは「鑑定士」という意味。
ウイスキーのあらゆる知識や鑑定能力を問う資格制度となっているそうです。
現在、第1段階のウイスキーエキスパート合格者は2400名程度(2020年までのデータ)。
毎年300~400名程度の受験者がいて、190名ほどの合格者が出ています。
酒類の輸入・流通・販売会社の方からバーテンダー・飲食業界の方が多く受験しています。
また、最近では、酒類業界に入りたい学生の方の受験も増えているそうです。
ウイスキープロフェッショナルとは?

ウイスキーコニサー試験の第2段階である「ウイスキープロフェッショナル」。
毎年3月ぐらいから申し込み受付を開始、5月下旬に試験が行われます。会場は東京と大阪の2会場。
受験料が24000円ほどとなっています。
ウイスキープロフェッショナル受験者データ
ウイスキープロフェッショナルの合格者は2021年現在、430名ほど。
直近の2021年の試験では、106名の方が受験し48名の合格者が出たそうです。
大体毎年、合格率は40~45%となっています。
詳しいデータは「ウイスキー文化研究所の受験者データ」をご覧ください
ウイスキープロフェッショナルの難易度

合格率40~45%前後と資格試験としては、合格率は中程度と思います。
ただやって思いましたが、ウイスキープロフェッショナル試験はかなり難易度の高い試験です。
ウイスキープロフェッショナル試験で僕が難しいと思う点は3点。
- ある程度完璧にウイスキーの知識を覚える必要がある。
- 「書くこと」に慣れていないといけない。
- 文章読解力や表現力も問われる。
まず、ウイスキープロフェッショナル最大の特徴が記述試験であること。
第1段階のウイスキーエキスパート(WE)はマーク試験でした。
そのため……
大麦の英語名とは?英語で次の中から選びなさい。
- malt
- barley
- cereal
- grain
この答えは、
①のmaltは、「大麦麦芽」のこと。発芽しているかしていないかで英語名が変わるので要注意が必要なところです。
また③のcerealは「穀物」の総称を指すことがありますが、基本的には穀物加工食品のことを指します。
そして④のgreinは収穫された穀物のこと。
このようにウイスキーエキスパート試験では、選択肢があります。
今回の問題なら、cerealとgrainはともに「穀物」を指す言葉として消去して、実質2択として考えることも可能。
ヒントがあることがウイスキーエキスパートの特徴なので、正直ある程度ならうろ覚えでも合格できる試験です。
しかし、ウイスキープロフェッショナル(WP)の場合……
ウイスキーのオフフレーバーのもととして有名なものを2つ挙げてください。
問題文としては、このようになります。
全くのノーヒントです。
答えは……
それぞれ硫黄化合物の一種。
DMSは、硫化メチル。
悪臭・公害の原因物質の一つとなっているそうで、腐ったキャベツのようなにおいが特徴となっています。
そしてDMDSは、二硫化メチル。
硫化メチル同様の不快な香りの原因となる物質です。
この二つは、ウイスキー蒸留時にポットスチルの銅材と反応して取り除かれることの多い成分であり、またウイスキーの熟成により揮発していくといわれています。
この学生時代の化学のテストのような問題もよく出ていきます。
しかもそれがノーヒントです。うろ覚えでは絶対にこたえられません。
問題内容の難しさから、ウイスキープロフェッショナルはお酒関連の資格の中では難しい試験だと思います。
また、ウイスキープロフェッショナルは、「書くこと」にも慣れていないとかなり厳しい試験。
なぜなら、とにかく文章で回答する問題が多い!ということ。
例えば……
発酵性糖類とは?次の中から選びなさい。
- 単糖または、二糖から四糖までの糖類でα‐1.6結合を含まないもの。
- ブドウ糖、麦芽糖のみ
- 四糖からデキストリン
- 酵母や乳酸菌が資化できる糖類
この場合の正解は、
です。
②と③は論外。④は言っていることは間違っていないですが、ウイスキーの試験の場合、発酵性糖類は酵母が資化できる糖類で考えられます。
そのため、①が正解となります。
このようにウイスキーエキスパート試験ではある程度文章が書いてあり、そこから選ぶスタイル。
ただウイスキープロフェッショナルの場合……
麦芽粉砕時の粒径で、基本ハスク:グリッツ:フラワー=2:7:1となっている理由をお答えください。
このような問題があり、これに対する一つの回答例が……
ここまで書いて正解となります。
ポイントは3つ
- ハスクがろ過材として必要
- 粒径の小さいフラワーは、エキスや糖分を多く得るけど、香味成分生成を阻害する成分も多く出る。
- 程よいグリッツを多くする必要がある。
この3つが文章でうまく伝えられるのならば、もっと端的にまとめることはできると思います。
ただこのぐらいの解答の問題が1点で10問以上はあります。下手したら20問近くはあるんじゃないかな……。
試験時間は90分なので、記述に慣れておかないと時間ギリギリかすべて書ききれません。
そして文章をうまくまとめる能力も問われると思います。
短くまとめないととてもじゃないけど書ききれないし、見直しの時間も取れないです。
なので、「書くこと」への慣れと文章をまとめる力も少し必要になってきます。
そして官能テイスティング試験で最も問われるのは、「表現力」だそうです。
官能テイスティング試験では、4種類のウイスキーのブラインドティスティングが行われます。
銘柄を隠した状態でテイスティングし、アロマ・特徴・余韻などをマーク形式で埋めて、どこのウイスキーか自分の考えを書きます。
そして最後にこのウイスキーに対するコメントを書くのですが、このコメントに対する配点が大きいそう。
銘柄を隠したウイスキーの味わいや自分なりの表現が問われます。
- うろ覚えでは合格できない。
- 「書くこと」に慣れていないといけない。
- 表現力も問われる。
この3点が僕がウイスキープロフェッショナル試験で難しいと思うポイントです。
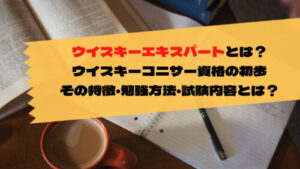
ウイスキープロフェッショナルの資格を取得するメリット

そんな難しいウイスキープロフェッショナル試験。
資格取得してよかったと思う点は3点あります。
- お酒業界、飲食業界なら仕事に活かせる。
- ウイスキーの知識がかなり深くなる。
- ウイスキーレクチャラー養成講座を受ける資格を得ることができる。
まず、お酒業界、飲食業界で「ウイスキーコニサー」資格のことを知っていれば、転職や普段の業務の面で仕事に活かせる点が多くあります。
またウイスキーエキスパートではうろ覚えでも取れる資格のため、実際お客様相手にしたときに「答えられない・わからない」となってしまうことは多々あります。
ところが、記述試験の「ウイスキープロフェッショナル」では、いやでも覚えています(笑)。
特にウイスキー製造の面で、パッとこたえられることが多いです。
つまり、ウイスキープロフェッショナルの資格が大きな影響を与えるというより、その勉強プロセスが仕事にいい影響を与えると思います。
そして、ウイスキーに対する知識がかなり深くなったので、ウイスキープロフェッショナルを獲得してからウイスキー蒸留所見学に行くとまた違った見方ができます。
「この作り方をしているから、この工程からこういったウイスキーの味わいを求めているのか」と想像できるようになりました。
そしてウイスキープロフェッショナル有資格者のみが受けられる「ウイスキーレクチャラー養成講座」。
この講座を受けてウイスキーレクチャラーになると、TWLC(東京ウイスキー&スピリッツコンペティション)の審査員に選ばれることがあります。
ウイスキープロフェッショナルの資格の価値より、そこで努力したプロセスやその後の仕事などにメリットがたくさんあると思います。
ウイスキープロフェッショナルの勉強方法

僕がおすすめしたいウイスキープロフェッショナルの勉強方法は、4つ!
- ウイスキー文化研究所の「コニサー教本」をノートにまとめる。
- 時間を計りながら、ひたすら過去問題集を解く。
- ウイスキー最新情報は「ウイスキーガロア」をチェック。
- ひたすらオフィシャルスタンダードのウイスキーをテイスティングする。
ウイスキー文化研究所の「コニサー教本」をノートにまとめる。





現在、上・中・下と3部に分かれているウイスキーコニサー教本。
基本的にこの内容が試験内容となります。特に製造面での文章問題は、この教本に書かれている内容をまとめる必要があります。
そのため、僕はまずこの教本を書いてまとめるところから始めました。
特に注意点は、教本の小さい文字で書かれているところです。
本文をまとめることはもちろんですが、教本の「※」印後の小さい文字の部分は、過去問と実際の試験の時を見る限り必ずどこか出ます。
ここに書かれている内容は、「α₋アミラーゼ、β₋アミラーゼの違い」「ウイスキーの乳酸発酵の意味」など。
こういった細かい内容をまず自分の言葉でまとめてみることが有効だと思います。
一見非効率な方法ですが、書くことに慣れつつ知識を入れていくことができるので効率のいい方法かなと思います。
時間を計りながら、ひたすら過去問題集を解く。
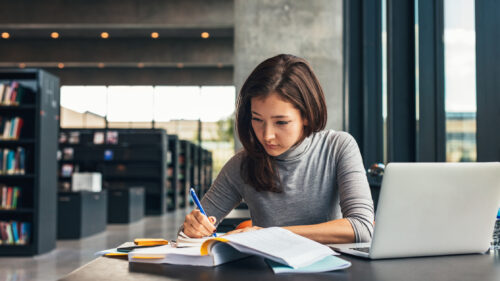
ウイスキープロフェッショナル試験の対策は「とにかく書くこと」が一番重要だと思います。
ウイスキーに対する深い知識も求められますが、過去問や教本を書いているうちに身についていきます。
そして時間を計りながら過去問を解き続けることで、「ここはこうまとめた方がいいかも」というものが出てくると思います。


ただ一ついえるのが、ウイスキープロフェッショナルにおいて解答は一つではないこと。
自分なりのまとめ方で要点が抑えられていれば得点を得ることができます。しかし、要点がずれていると正解にはなりません。
過去問題集の解答を見ても解説がないので、要点は自力で探すしかありません。
まずは、過去問題集の解答を覚えて、そこから「質問」に対する要点を探すものありだと思います。
※現在ウイスキーエキスパート過去問題集しか無く、ウイスキープロフェッショナル過去問題集が手に入らないようです。
ウイスキー最新情報は「ウイスキーガロア」をチェック。


ウイスキーの最新情報は、ウイスキー文化研究所が出版している「ウイスキーガロア」からチェックするといいと思います。
各号主テーマについて深くまとめてあり、新入荷のウイスキーやガロアテイスターによるウイスキーテイスティング評価などの情報が載っています。
ウイスキープロフェッショナルを勉強するうえでかなり勉強になる雑誌ですし、ウイスキーを深く勉強するうえでも参考になる雑誌だと思います。
ひたすらオフィシャルスタンダードのウイスキーをテイスティングする。

ウイスキープロフェッショナルの官能テイスティング試験では、基本的にはオフィシャルスタンダードしか出てきません。
そのため、オフィシャルのスタンダードボトルを飲んでテイスティングし、その違いを把握しておけば十分だと思います。
またウイスキーオフィシャルを再度飲んでみると、また違いが判り、新しい発見もできるはず!
ぜひ楽しみながら勉強していただけたらと思います。
ウイスキープロフェッショナル予想問題

最後に、予想問題と僕なりの解答例、解説をまとめました。
ちなみにプロフェッショナル向きに問題は選択式ではないです。
なので、記述形式で問わせていただきます。
問題
問1、モルトウイスキー視点で麦芽(モルト)とは何か?一行で答えてください。
⇨答え
問2、大麦の古代品種ベア種のアルコール収量は?
⇨答え
問3、現在の優良品種とされている(オプティック、コンチェルト、オデッセイ)のアルコール収量は?
⇨答え
問4、製麦の目的を3つ挙げてください。
⇨答え
問5、非発酵性糖類とは?
⇨答え
解答

問1、モルトウイスキー視点で麦芽(モルト)とは何か?一行で答えてください。
試験用の答え方は人とそれぞれでいいと思いますが、「発芽」・「酵素」・「活性化」は入れたほうがいいと思います。
問2、大麦の古代品種ベア種のアルコール収量は?
LPA/麦芽トンという単位は覚えましょう。LPAはリッター・ピュア・アルコールの略。
簡単に言うと「麦芽1tから100%アルコール換算で、〇〇ℓのアルコールができます。」という値です。
仮に50%のアルコール度数でウイスキーを造っているとしたら520ℓを生産しているということです。
問3、現在の優良品種とされている(オプティック、コンチェルト、オデッセイ)のアルコール収量は?
2020年時点では、このぐらいです。
覚えましょう。
問4、製麦の目的を3つ挙げてください。
ここも言い回しは自分の文でOK。
ただし、
1.は「発芽」・「酵素」「生成・活性化」は重要かと思います。
2.は「溶けの良い」・「溶けやすい」が重要です。
3.はつまり「ピート燻製によるスモーキーフレーバーの付加」です。しかし「ピート燻製による」という言葉を使うと断定的になりやすいのであえて伏せた文章のほうが、点が取りやすいと思います。
問5、非発酵性糖類とは?
発酵性糖類か非発酵性糖類かは、酵母が資化できるかどうかで決まります。
酵母は、環構成の糖を一つの単位として、
- 一つだけのもの「単糖」……グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)など
- 2つ結合したもの……マルトース(麦芽糖)、スクロース(ショ糖)、ラクトース(乳糖)など
- 3つ結合したもの……マルトトリオースなど
- 4つ結合したもの……マルトテトラオースなど
がアルコール発酵にしかできる糖類となります。
さらに、環構成同士の結合にα₋1.6結合があると酵母は資化することができません。
最後に……

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回のお話はいかがだったでしょうか?また予想問題の結果はいかがだったでしょうか??
難しく勉強方法も書きましたが、一番はウイスキーを楽しむことだと思います!!
ぜひ楽しみながら、ウイスキーの資格勉強してみてください!
ご受験される方、応援しています!!
それでは、良いウイスキーライフを!!
また次回もよろしくお願いいたします!
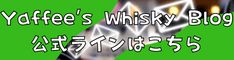
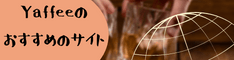
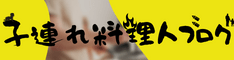
↑↑
公式ラインページにて当ブログの更新情報など不定期配信しています。
また、「子連れ料理人ブログ」では子育て・料理人としての働き方・副業(主にブログ)についての内容を配信中。
ご興味のある方は、一度お越しください!!
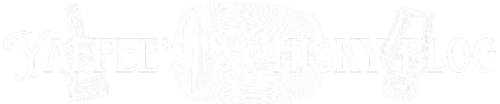







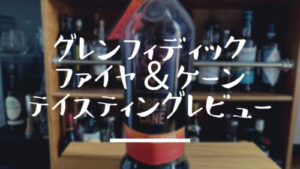
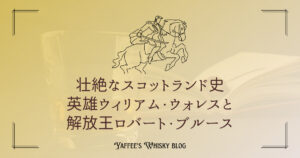








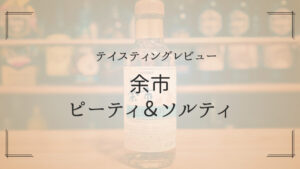
コメント
コメント一覧 (2件)
Oni-Taijiさん>ありがとうございます。
正直試験を受けない人はよくわからないと思いますが……。
Zarugawaさん>
難しいですよね。それだけ為になるし、よりウイスキーが好きになると思うので気になったらぜひエキスパートから!