ウイスキー造りに欠かせない酵母。
様々な種類のある酵母ですが、ウイスキーには主に使われる酵母はエール(ビール)酵母とディスティラリー酵母です。
酵母の違いや発酵工程によって出来上がるウイスキーの香味に違いが生まれます。
発酵はアルコールを作る大事な工程ですが、それだけではありません。
実は、ウイスキーの香味を左右する大事な工程でもあるのです。
今回は酵母と発酵工程に着目しつつ、ウイスキーの香味にどのように影響するのかまとめました。
『酵母』とは??

酵母とは、糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物のことです。
カビやキノコと同じ真菌類で、空気中や果物・野菜の表面など自然界の様々なところに生息しています。
古来からアルコール発酵からパン発酵、熟成など幅広く活用されてきました。
特にアルコール発酵は糖と水があれば行われるため、人類誕生より歴史が長いといわれています。
酒造りに必要な酵母の種類

酒造りに使う酵母は基本的には1種類のみです。
酵母は学名で『サッカロミセス・セレビシエ(サッカロマイセス・セレビシエ/サッカロミケス・セレビシエ)』という「出芽酵母」と呼ばれています。
同じサッカロミセス・セレビシエでも亜種は多様です。
- ワイン酵母
- 清酒酵母
- パン酵母
- ディスティラリー酵母
- エール酵母
など
同じ酵母でも炭酸ガスの発生量やアルコール収率、成分される副産物などが違います。
 yaffee
yaffeeサッカロミセス・セレビシエはいわば人に例えたら「ホモサピエンス」みたいなものかな。多様な人種がいるのと一緒だと思う
ビールや日本酒では、酵母を使い分けて醸造されるところが多いですが、近年ウイスキーでも注目が集まっています。
実はあった例外のアルコール発酵


『酒造りに使う酵母はサッカロミセス・セレビシエの1種類のみ』と前記しましたが、例外があります。
- サッカロミセス・パストリアヌス
- ザイモモナス・モビリス
- シゾサッカロミセス・ポンベ
サッカロミセス・パストリアヌス
世界中で飲まれているラガービールの発酵に使われている「ラガー酵母」は、サッカロミセス・パストリアヌスです。
サッカロミセス・セレビシエとその近縁種であるサッカロミセス・ユーバヤヌスの雑種となります。
ザイモモナス・モビリス
ごく一部のテキーラでは、ブルーアガベが持っていた常備菌であるザイモモナス・モビリスという細菌もアルコール発酵させることがあります。



酵母といっしょにアルコール発酵していたそう。


この菌が確認できているお酒は、テキーラとその前の段階のプルケのみです。
シゾサッカロミセス・ボンベ
アフリカの伝統的なミレットビール(ポンべ)から発見されたシゾサッカロミセス・ポンべ。


サッカロミセス・セレビシエとは分裂の仕方・増え方が違います。
そして実はこの酵母が使われているウイスキーがあります。
2018年のディアジオスペシャルリリースの一つ、『グレンエルギン18年』です。
※2018年ディアジオスペシャルリリースのグレンエルギン18年ではない可能性があります。
一部、ボンベ酵母を使った原酒が使われています。
ウイスキーと酵母の関係


多彩な酵母の中でもエール酵母とディスティラリー酵母が主にウイスキーに使われます。
| エール酵母 | イギリス伝統のエールビールに使われる酵母 |
|---|---|
| ディスティラリー酵母 | 1950年代に蒸留酒造りの適正に合わせて開発された培養酵母。 |
エール酵母とディスティラリー酵母


ウイスキーは昔からビール醸造所から余ったエール酵母が使われてきました。
エールビールの製造工程では、酵母が余ってしまうことが多いです。
ディスティラリー酵母が開発される前は、余った酵母をウイスキー蒸留所で活用してもらう流れが一般的でした。



ウイスキー自体も当時は地元もお酒程度なので、余剰酵母で間に合っていたんだろうね。
1950年代に生産効率のいいディスティラリー酵母が開発されます。
アルコール収率に優れていて、エール酵母に比べて発酵も早いことが特徴。
現在ではディスティラリー酵母がメインで使用されています。
| エール酵母 | ディスティラリー酵母 | |
|---|---|---|
| 発酵時間 | 長い | 短い |
| アルコール収率 | 低い | 高い |
| 発酵能力 | 低い(他の酒類より強い) | 高い |
| 酒質 | 芳醇な香味 | クリーンでエステリーな香味 |
エール酵母とディスティラリー酵母、併用が最強
ディスティラリー酵母とエール酵母を併用したら、よりウイスキーの品質が向上することが判明しました。
酵母は栄養分が枯渇した時、生命維持のために必要な成分をため込みます。
その状態を成熟酵母と言い、ウイスキーの複雑みを増す重要なポイントです。
ディスティラリー酵母は成熟酵母になりますが、通常エール酵母単体では成熟酵母にならず死滅してしまいます。
ディスティラリー酵母とエール酵母を併用すると、エール酵母も成熟酵母となり生存。
| エール酵母 | 混合 | ディスティラリー酵母 |
|---|---|---|
| 成熟酵母にならない | 両方とも成熟酵母になる | 成熟酵母になる |
するとエール酵母単体で使用した時より多様な成分が生まれ、ウイスキーに複雑みが与えられると考えられています。



1+1が2ではなく、3になったようなもの
この実験結果を踏まえて、酵母を併用する蒸留所もあるようです。
(参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/5/101_5_315/_pdf/-char/ja、
古賀邦正著:ウイスキーの科学 熟成の香味を生む驚きのプロセス)
ウイスキーの発酵工程


ウイスキーの発酵工程は、大きく5つの手順があります。
- 麦汁の冷却
- 発酵槽へ移す
- 酵母投入
- 酵母が糖からアルコールを生成
- 発酵液(モロミ)の完成
麦汁の冷却
麦汁は、でんぷんを糖化しやすい60℃前後の温度で抽出されますが、この温度では酵母は死滅してしまいます。
そのために、酵母が活動しやすい20~22℃程度まで麦汁を冷却する必要があるのです。
その方法は、かつてはオープンワーツクーラーという自然冷却の簡易的なコンデンサーを使っていました。
今でも使っている蒸留所はスコットランドのエドラダワー蒸留所です。
今では熱効率がいい熱交換器(ヒートエクスチェンジャー)が主流となっています。
発酵槽へ
冷却された麦汁を発酵槽へ移していきます。


この時、発酵槽の材質によってウイスキーの香味に大きな影響を与えます。
ステンレス製と木製(ダグラスルファ―など)の発酵槽がありますが、現在の主流はステンレスタンクです。
ステンレス製は、温度管理や細菌管理、清掃が容易という利点があります。
ところが、木製の方が乳酸菌などの発酵が促進しやすいという傾向があり、どちらを採用するかは蒸留所次第です。



木が菌の「住み処」となるみたいだね。
| ステンレス製発酵槽 | 木製発酵槽 | |
|---|---|---|
| メリット | 温度や菌の管理がしやすい 比較的メンテナンスが楽 | ステンレス製より、常備菌が多い 発酵しやすい |
| デメリット | 木製発酵槽より常備菌が少ない | メンテナンスが大変 |
中には、両方とも保有し使い分けている蒸留所もあります。
酵母の投入
発酵槽に移した麦汁に酵母を投下していきます。


前記したように主にウイスキーに使われる酵母は『ディスティラリー酵母』や『エール酵母』です。
どちらも培養酵母で、ウイスキーには野生酵母が使用されることはほとんどありません。
ウイスキーはビールのようにホップの投入や麦汁の煮沸消毒が行われないため、複雑に様々な微生物が存在しています。
酵母のアルコール発酵が優位に行われるようにビールより多めの酵母が投入されます。
アルコール発酵
投入すると徐々にアルコール発酵が起きていきます。
| 酵母繁殖期 (発酵開始~15時間程度) | 酵母が増え、濁り始める 糖、アミノ酸が減る 華やかな香り |
|---|---|
| 酵母最盛期 (15~40時間程度) | 温度上昇 糖、アミノ酸が大幅に減少 酵母の数がピークに |
| モロミ熟成期 (40~72時間程度) | 死滅酵母が増える 乳酸菌が発生、乳酸ができる 酸っぱいにおい |
アルコール発酵開始から大体15時間ぐらいまで、酵母は糖やアミノ酸を食べアルコールを生成し増殖します。
増えた酵母によって麦汁は濁って見え、徐々に華やかな香りとなります。
その後15~40時間程度が発酵最盛期です。
酵母によってモロミの温度が上昇、炭酸ガスやアルコールの生成量が増えていきます。
反して糖とアミノ酸は減少。
酵母のえさとなる糖やアミノ酸が減少すると酵母の増殖もストップします。
発酵開始から40時間後、酵母自身が生成したアルコールと糖分・アミノ酸の減少により死滅酵母が増えていきます。
そして死滅した酵母の体内からアミノ酸が流出。
アミノ酸と多糖類(非発酵性糖類・酵母が取り込めない結合サイズの大きい糖類)を栄養に乳酸菌が乳酸を生成します。
| 発酵時間が短い | 穀物様のある重い香味の酒質 |
|---|---|
| 発酵時間が長い | 軽くすっきりとした香味の酒質 |
むせ返るような酸っぱいにおいとなりますが、ウイスキーでは乳酸発酵も重要な発酵工程です。


モロミの完成
ビールの場合ろ過をして酵母を取り除くことが多いですが、ウイスキーは死滅した酵母や乳酸菌を残したまま蒸留します。
死滅した酵母が蒸留時に様々な香味を生むポイントとなるようです。
酵母がウイスキーにもたらすこと


酵母はアルコールと炭酸を造るだけではありません。
酵母は、香りや味に影響する副産物を作り出します。
- エタノール
- プロピルアルコール
- イソブチルアルコール
- アミルアルコール
- イソアミルアルコール
- グリセロール
- 酢酸
- カプロン酸
- カプリル酸
- ラウリン酸
- パルミチン酸
- 酢酸エチル
- 酢酸エステル
- エチルエステル
酢酸エチルや酢酸エステル、エチルエステルなどのエステル類はフルーティな香りやフローラルな香りの元となる成分です。
またカプロン酸やカプリル酸などの成分もアルコールと反応し、エステル化することもあります。



エステル類はフレーバーエッセンスや香水の成分としても有名。
前に知多蒸留所や富士御殿場蒸留所に見学にいたせていただいたとき、スチルと酵母が違う原酒を飲み比べさせてもらったことがあります。
この時にお互いのヘビータイプの原酒に共通して感じた「鰹節、出汁」のような香り。
これは、両蒸留所とも「酵母由来の成分も多い」とおっしゃっていました。
バーボンなどアメリカンウイスキーの蒸留所では、自家培養酵母を使う蒸留所も多くあります。
中には数百種類の酵母の中から選んで使うところもあるようです。



自家培養の酵母だとフォアローゼスが特にこだわっているみたい。
酵母以外で役立っている菌、微生物


乳酸菌が名助演!!


酵母以外でウイスキー造りにはもう一つ欠かせない菌があります。
それは、乳酸菌です。
酵母のアルコール発酵の後に乳酸菌による乳酸発酵が起こります。
死んだ酵母と酵母が食べられない大きい糖分を栄養に乳酸菌が活動。
生まれた乳酸によって発酵槽の中はむせかえるような酸っぱいにおいになります。
これがウイスキー造りには必要なのです。
ポットスチルの材質は銅です。
その銅は、モロミの中にある硫黄化合物(オフフレーバーの元)を除去することができます。
ところが、使い続けると銅の表面に硫黄と銅が反応した物質や汚れが付着。
これをきれいにするのが乳酸です
乳酸によってポットスチルの内側を常にきれいにすることができるそうで、硫黄成分をより取り除きやすくしてくれます。
乳酸発酵を促したモロミを蒸留すると、硫黄系の香りが少ないライトな酒質になりやすいです。


蒸留所にも「蔵つき」がいる!!


今までウイスキーの発酵工程について書いていきましたが、実は糖化工程でも菌に関する面白い研究結果があります。
とある蒸留所でステンレス製の糖化槽の中の菌を大掃除前後に採取。
ほとんどの菌がいなくなっていることを確認するまで徹底的に掃除しました。
そして、稼働を始めて1~2週間後もう一度糖化槽の菌を再び調べてみたところ……。
大掃除前と全く同じ菌たちがいたそうです。
そこで別の蒸留所でも同じことをしたら、全く同じ結果になりました。
使っていた麦芽にもついていない菌もおり、蒸留所の常備菌だということがわかりました。
日本酒の酒蔵では「蔵つき」という言葉があります。
蔵に住み着いている酵母など常備菌のことで、この微生物たちが日本酒に命を吹き込んでいるという考え方です。
ウイスキーでも同じことが言えるようです。
最後に……


最後までお読みいただきありがとうございます。
今回のお話いかがだったでしょうか?
ウイスキーでも微生物の働きによって、味わいが大きく左右されます。
酵母はもちろん乳酸菌、蒸留所の常備菌などの助けもあり、琥珀色の美酒は完成しているのです。
ところが、現在「酵母の違い」まで分かるウイスキーはマニア向けの限定品しか味わうことができないでしょう。
さらに大々的に酵母の違いを紹介しているメーカーはありません。
それだけウイスキーで酵母の違いを紹介することが難しいのだと思います。
蒸留所見学などに行くと、まれに酵母の違いの原酒を試飲できる機会があります。
よりマニアックにウイスキーを楽しむために蒸留所見学の旅に出かけてみるのはいかがでしょうか?
ほかの製造工程に関する記事
⇩⇩⇩
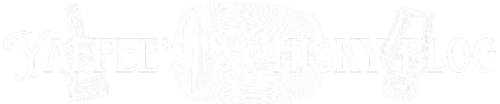











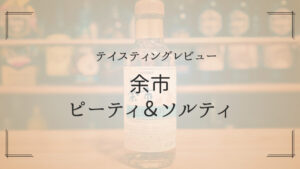
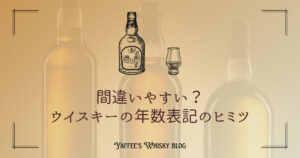
コメント
コメント一覧 (1件)
Zarugawaさん>酵母って調べてみると奥が深くて面白いんですよね。