スコッチウイスキーと呼ぶためには、最低限6つの定義を守らないといけません。
そして6つの定義を知ると、スコッチウイスキーの作り方がわかりやすくなります。
今回は、スコッチウイスキーの定義から作り方を解説していこうと思います。
スコッチウイスキーの定義

「スコッチウイスキー」は、英国の法律で以下のように定められています。

- 水・イースト・麦芽(モルトウイスキー)又はその他の穀物(グレーンウイスキー)のみを原料とすること。
- スコットランドの蒸留所で糖化・発酵・蒸留を行うこと
- アルコール度数94.8%以下で蒸留すること
- 容量700ℓ以下のオーク製の樽で熟成させること
- スコットランド国内の保税倉庫で3年以上熟成させること
- 水とスピリッツカラメル以外の添加は禁止。
スコッチウイスキーと呼ぶためには、この6つの定義を守らないといけません。
一つ一つウイスキーの製造工程から解説していこうと思います。
原料は、水・イースト・穀物のみ
スコッチウイスキーと呼ぶためには、水・イースト・麦芽またはその他の穀物だけで作る必要があります。
穀物以外を使用した場合やそのほかの材料を足した場合は、スコッチウイスキーではありません。
| サトウキビで作られた場合 | ラム |
|---|---|
| 果物で作られた場合 | ブランデー |
| 麹を足した場合 | 焼酎 |
 yaffee
yaffee麹でウイスキーを作ろうとしたところもあったみたいだけど、「スコッチウイスキーではない」と判断されたみたいだね。
また麦芽は穀物(主に大麦)を発芽させたものですが、「水・イースト・麦芽」と「又はその他の穀物」の記載をなっています。
- 「水・イースト・麦芽」はモルトウイスキー
- 「又は、その他の穀物」はグレーンウイスキー
それぞれ区分するための記載ともいえるでしょう。
スコットランドの蒸留所で糖化・発酵・蒸留
ウイスキーの製造工程は、
- 製麦
- 糖化
- 発酵
- 蒸留
- 熟成
- ブレンド
- 瓶詰め
です。
その上でスコッチウイスキーは、国内の蒸留所で糖化・発酵・蒸留までは一貫して行わないといけません。
例えばビール工場に発酵まで委託したとしましょう。
その後、蒸留所で蒸留したとしても、「スコッチウイスキー」を名乗ることができなくなります。
同じグループ会社内でも製造途中の糖化液やモロミを移動させることは、ご法度です。
その理由は、糖化・発酵・蒸留がウイスキー原酒のポテンシャルに大きく影響を及ぼすからでしょう。
それぞれの工程について詳しくはこちら
⇩⇩⇩
ちなみに、蒸留所内にビール工場がある場合は、問題なくビール工場のラインを使うことができます。
「エデンミル」という蒸留所が施設内にビール醸造所があり、ビールやジン、スコッチウイスキーを作っています。
蒸留上限アルコール度数は94.8%
蒸留は、蒸留回数が増えるほどアルコール度数は増えていきます。
スコッチウイスキーは、本来ポットスチル(銅製の単式蒸留器)で2回蒸留されており、アルコール度数は65~75%程度が一般的です。
ところが連続式蒸留機の登場により、90%以上のスピリッツを作られるようになりました。
- 熟成が早い
- 原料や発酵由来の個性が残りにくい
- 安価
お酒はアルコール度数が高いほど、上のような特徴があります。
高いアルコール度数で蒸留したお酒は熟成のピークが早く、長期熟成には不向きです。
また原料や発酵由来の個性が少なく、単体で飲まれることはほとんどありません。
スコッチモルトウイスキーには不向きな原酒であるため、連続式蒸留機での蒸留はグレーンウイスキーのみです。
蒸留上限アルコール度数は、品質を守るために必要な規則と言えるでしょう。



反対にジンの蒸留アルコール度数は96%以上。ジンとウイスキーを分ける区分とも言えるね。
樽はオーク製で容量が700ℓ以下
樽は大きいほど熟成が遅くなり、小さいほど熟成が早くなる傾向があります。
- バレル(180~200ℓ)
- ホグスヘッド(250ℓ)
- バット(500ℓ)
700ℓを超える大きさの樽では、ほとんど熟成が進みません。
そのため、700ℓ以下という決まりがあるのです。


また樽の材質は古くからオーク材が使われてきました。
- 強固で液漏れしにくい。
- ウイスキーの熟成に望ましい香味を得ることができる。
スコッチウイスキーの熟成樽は、オーク製の樽のみ。
それ以外の木材を使うと、スコッチウイスキーとは名乗れません。


さらに、スコッチウイスキーはほかのお酒が入っていた樽で熟成されることが多いです。
2019年にスコッチウイスキーに使える樽の種類にも細かい決まりができました。
スピリッツは、オークの新樽や、ワイン(無発泡性ワインおよび酒精強化ワイン)、ビール(エール)、スピリッツ類などの熟成に使用したオーク樽に入れて熟成されるものとする。ただし下記の酒類を熟成したオーク樽は除外する。
• 原料に核果が含まれるワイン、ビール(エール)、スピリッツ
• 発酵後に果実、フレーバー、甘味が加えられたビール(エール)
• 蒸溜後に果実、フレーバー、甘味が加えられたスピリッツ
• 上記の製法を伝統的に採用しているワイン、ビール(エール)、スピリッツ使用する樽の種別に関わらず、完成された製品はスコッチウイスキーの伝統的な色、味、アロマの特徴を示していなければならない。これらの条件は、以下で説明する後熟工程においても同様である。樽に入っていた内容物は、スコッチウイスキーまたはスコッチウイスキーとなる予定のスピリッツを容れる前に完全に排出されなければならない。
(※スコットランドの飲料に関する検証機構:技術指導書(スコッチウイスキーの検証)2019年6月改定)
ワインやビール、スピリッツの熟成に使われていた樽ならOKとなります。
焼酎やテキーラなどの樽でも熟成させることが可能。
ところが、以下の樽はNGとなります。
- 核果(梅、アンズ、桃などのフルーツ)が含まれるワイン・ビール・スピリッツ
⇨キルシュ、梅酒、アプリコットワインなど - 発酵した後にフルーツや甘味、フレーバーが添加されたビール
⇨フルーツビール、ランビックなど - 蒸留後にフルーツや甘味、フレーバーが添加されたスピリッツ
⇨ジン、リキュール類など
スコットランド国内で3年以上熟成


スコッチウイスキーと呼ぶためには、スコットランド国内で3年以上熟成させる必要があります。
スコットランド国内の英国内国歳入関税庁(HM Revenue& Customs)により登録を受けた保税倉庫であれば、どこの倉庫で熟成させてもOKです。
- 蒸留所Aで作られたウイスキー原酒を蒸留所Bの熟成庫で熟成させた。
- アイラ島で作ったウイスキー原酒をグラスゴーの保税倉庫で熟成させた。
これらは許可されています。



コレ、結構な確率でウイスキープロフェッショナルの試験に出るので、試験を受ける人は覚えておくように……!
関税庁の登録された倉庫である理由は、ウイスキーは熟成中から酒税の対象となるからです。
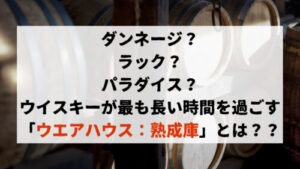
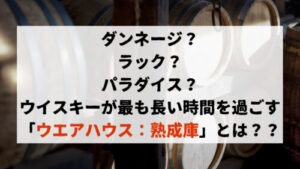
水とカラメル(着色用)以外添加できない
水やカラメル(着色料)以外をウイスキーに添加することは許されていません。
逆を言うと、着色料としてカラメルを添加することは許されています。
ウイスキーは一つの樽ごとに味も違えば色合いも違います。
同じ味・同じ色に仕上げるためには、どうしても着色しなくてはいけないときがあるのです。
特にブレンデッドウイスキーでは着色されていることが多く、着色されてないウイスキーには「NO-COLOR」と記載されています。
カラメルも使用できるカラメル色素には、決まりがあり、糖分だけで作られたカラメル以外は使えません。



中には、アンモニア化合物や亜硫酸などを加えてつくられるカラメル色素(食品添加物)もあるよ。
また、多くのウイスキー銘柄は、アルコール度数40%程度に加水調節されています。
アルコール度数40%がスコッチウイスキーと呼べる最低アルコール度数のため、そのアルコール度数まで加水調節されてボトリングされるのです。


スコットランドに限らず、アイルランドや日本、アメリカでも甘みやフレーバーを添加した場合ウイスキーではなくなります。
特にスコッチウイスキーでは、
- モルトウイスキー原酒
- グレーンウイスキー原酒
- 度数調整のための水(アルコール度数40%以上)
- 色調整程度のカラメル
以外のものを添加した時点でウイスキーではなくなると法で決められています。
最後に……


最後までお読みいただきありがとうございました。
今回のお話いかがだったでしょうか。
スコッチウイスキーの定義をおさらいすると……
- 水・イースト・麦芽(モルトウイスキー)又はその他の穀物(グレーンウイスキー)のみを原料とすること
- スコットランドの蒸留所で糖化・発酵・蒸留を行うこと
- アルコール度数94.8%以下で蒸留すること
- 容量700ℓ以下のオーク製の樽で熟成させること
- スコットランド国内の保税倉庫で3年以上熟成させること
- 水とスピリッツカラメル以外の添加は禁止
他にも
- モルトウイスキーはポットスチル(単式蒸留器)で作らないといけない。
- シングルモルトウイスキーはスコットランド国内で瓶詰しないといけない。(ブレンデッドウイスキーは国外でもOK)
などの細かいルールもあります。
このすべての定義を満たしていないと「スコッチウイスキー」と呼ぶことはできません。
このように細かい定義が定められているのは、スコッチウイスキーとしての品質を法で守るためです。
世界中で愛されている「スコッチウイスキー」が、一定のクオリティ以下にならないように厳しく定められています。
定義が作られたのは、600年以上もの歴史から培った経験にほかなりません。
そしてスコッチウイスキーの法律を参考に、日本を除く世界5大ウイスキーは法で定められています。
他の国の定義を知りたい方は、過去の記事(ウイスキーの定義とは??知っておきたいそれぞれのウイスキーのルールについて再確認!)をチェックしてください。
ウイスキーの定義を知ると、より蒸留所見学やウイスキーの説明がわかりやすくなると思います。
ウイスキーの定義を知り、よりウイスキーを深く楽しんでください!!
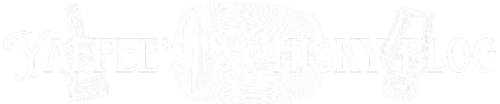


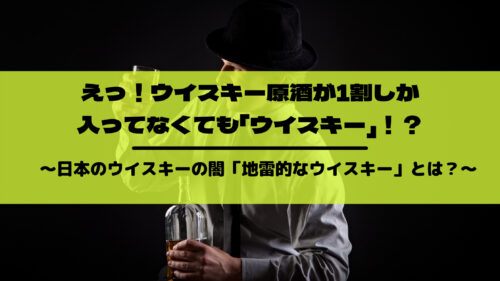









コメント